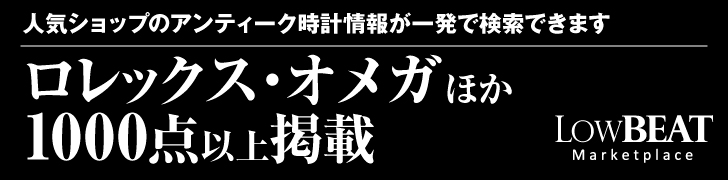アンティーク時計専門サイト「LowBEAT Marketplace」には、日々、提携する時計ショップの最新入荷情報が更新されている。
そのなかから編集部が注目するモデルの情報をお届けしよう。
日本の時計産業は、世界的に見ても後発であったが、戦後の経済成長と企業、職人、設計士たちの努力によって、現在では世界有数の時計生産国へと成長した。他国と比較しても尋常ではないスピードで研究開発が進められ、その過程でセイコー、シチズン、オリエントによって数えきれないほどのムーヴメントが開発された。そのなかにはいまなお名作として語り継がれるムーヴメントも数多く誕生している。そこで今回は、国産自動巻きの黎明期から成熟期にかけて製造された、特徴的な自動巻き機構を備える腕時計を紹介する。
まず1本目はセイコーのスポーツマチックだ。
1956年に初の自動巻き腕時計を製造したセイコーであったが、これはあくまでもスイス製のムーヴメントを参考にしたものであったうえ、部品点数や製造コストの面から高価になってしまい、一般層にはあまり普及しなかったとされている。そこで、自動巻きモデル第2世代に当たるジャイロマーベルでは “マジックレバー”と呼ばれる2股の爪とラチェット車を組み合わせたシンプルな構造によって両方向の自動巻きを低コストで生産することを可能にしたのだ。
そして今回紹介するスポーツマチックも、このマジックレバーを搭載したものであり、後の“セイコースポーツマチック5”、現在のセイコー5の源流にあたるモデルなのだ。

【写真の時計】セイコー スポーツマチック。GP(37mm径)。自動巻き。1961年頃製。2万8800円/WTIMES
この個体は1961年頃に製造されたもので、当時は若者を中心に人気を博したとされている。手巻き機構を廃することでコストダウンを図った設計が特徴的で、後のセイコー5シリーズにも受け継がれている。マジックレバーによる巻き上げ効率も十分で、始動時に数十回振る必要があるものの、歩行を伴う日常動作だけで1日は確実に動作するはずだ。
次に紹介するのは、オリエントのグランプリ64だ。
圧倒的な石数を誇るこのモデルは、1964年の東京オリンピック開催にあわせて、ムーヴメントに64個の石(人工ルビー)を使用したものであった。後にグランプリ100という100石仕様の製品も登場するが、どちらもすべての石がベアリングとして機能するわけではなく、半分以上は飾りとして使用されていたそうだ。

【写真の時計】オリエント グランプリ 64。SS(38mm径)。自動巻き(Cal.676)。1960年代製。16万8000円/ジャックロード
そんな同モデルの自動巻き機構には、IWCのペラトン式に似た構造が採用されている。偏心カムとローラー、ラチェット歯車の配列は、ほぼペラトン式自動巻きと同様であり、オリエントはIWCに倣って自動巻きを開発していたことがうかがえる。
また、力強いラグとインデックス、厚みのある防水ケースからもIWCの影響を感じることができる。裏ブタのメダリオンが特徴的なオリエントの高級機だ。
最後に紹介するのは、1971年に製造されたグランドセイコー 5646-7010だ。諏訪精工舎が製造したモデルであり、愛好家の間ではキャリバー名から“56GS”として親しまれている。今回取り上げた時計のなかで最も近代的な設計をもち、薄型かつ高精度である点が大きな特徴だ。

【写真の時計】セイコー グランドセイコー。Ref.5646-7010。SS(36mm径)。自動巻き(Cal.5646)。1971年頃製。7万6800円/WTIMES
このムーヴメントは、自動巻き機構に切替車(リバーサー)式を採用しており、省スペースかつ高い巻き上げ効率が特徴だ。主にスイスのメーカーが積極的に採用していた方式で、マジックレバーを主軸に置いていた諏訪精工舎としては斬新なムーヴメントであった。この自動巻き機構の利点を生かすために、通常では分針の役割をつかさどる2番車を中心からオフセットし、空いたスペースに自動巻き機構を埋め込むことでムーヴメントの薄型化に成功している。
いまでは当たり前となった自動巻き機構だが、現在に至るまでには、様々な試行錯誤が重ねられてきた。アンティーク市場には、いまとなっては非効率的とされる自動巻き機構も存在するが、それと同時に、奇抜なアイディアや設計が光る時計も数多く見受けられる。
ぜひ、誰かに自慢したくなるような、ユニークな機構を備えた一品を探してみてほしい。
文◎LowBEAT編集部